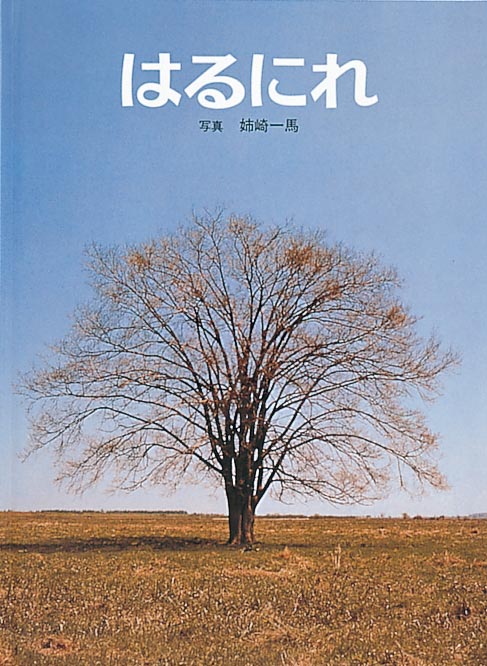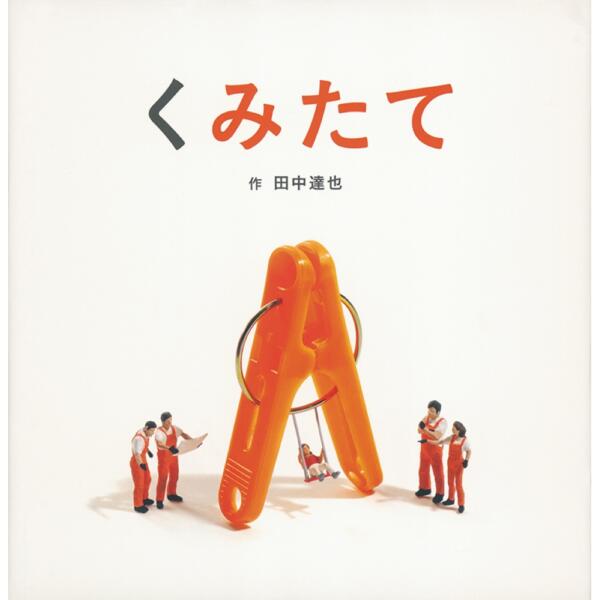3学期スタートしました!
穏やかなお天気の多かったひと月でしたが、お元気でお過ごしでしたでしょうか?冬休みの間は、昨年の大雪を思い出してドキドキしつつも、もう少しだけ、子ども達が思い切り遊べるほどの雪が欲しいなあと思いながら園庭を見つめていました。
さて、今日からいよいよ3学期がスタートします。きっとお友達と会えるのを楽しみにしていたことでしょう。同時に、長いお休みの後で、少し登園に不安を感じているお子さんもいるかと思います。園生活のリズムを取り戻すまで、心身ともにちょっと時間が必要かもしれませんが、笑顔で見守り、背中を押して頂けますようよろしくお願い致します。
3学期はこれまでのまとめでもあり、次のステップへの準備の期間でもあります。この一年の様子を思い出しながら、最初の頃はあんな風だったなあ…そして運動会の後にはこんな姿に変わったっけ…自分の言葉でたくさん話してくれるようになったなあ…友達と遊べるようになったなあ…楽しそうな表情がぐんと増えたなあ…などなど、成長の道筋を辿りながら、あの時、この時、とフラグを立てる事で、あらためてお子さんの様子を振り返る事ができます。
そこから、4月からの次の一歩に向けて、今のうちに経験させてあげたい事、身に付けて欲しい事、もう少しだけ上の方に引っ張って、励ましながらやり遂げさせてあげたい事、自信をつけてあげたい事など、一人一人へのテーマも浮かんできます。先生方も冬休みの間に自己評価を行い、2学期を振り返り、3学期の目標を立て、自分の姿と子ども達の育ちの姿を結び付ける作業を経て、新たな気持ちで今日を迎えました。驚くほどあっという間に過ぎる3学期だからこそ、一日ずつ、限られた時間を、大切に過ごしていきたいと思っています。
特に年長さんは、ランドセルの色、机、小学校の名前…そんな話題がよく子ども達から出てくる頃となります。どの子も嬉しそうに教えてくれますが、同時に卒園を淋しく思う時間もあるようです。淋しいと嬉しいが混在する時期、ちょっと感じやすくなるお子さんもいますが、園生活で育った人を信頼する力、友達を求める力、よく考える時間、人の話に耳を傾ける姿勢、それを大いに認め、「こんな事もできるようになったよね!」と一緒に確かめながら、より自信を持てるよう準備をしていきたいと思います。
この1年も、ご家族皆様が明るく健康で、そして笑顔で過ごせますよう心よりお祈りしております。本年もどうぞよろしくお願い致します。
園長 佐々木 圭子